イエスが歩いた土ぼこりの道をあなたも歩くことを想像したことがありますか? 足にほこりっぽさを感じ、カペナウムの街でアラム語が話されるのを聞き、ガリラヤ湖にきらめく太陽の光を見ることも想像できますか?
イエスの時代の生活を理解することは、単なる好奇心以上の意味があります。わたしたちの証を深めてくれるのです。イエスが生きた時代を理解すると、聖書の中のたとえ話はより鮮明に心に響き、数々の奇跡はさらに深い意味を持ち、そしてイエスが捧げた犠牲はあなたにとってひときわ個人的なものになるのです。
聖典はわたしたちをまったく異なる時代と場所へと連れて行ってくれます。そこは、深い信仰、政治的抑圧、祖先からの伝統、そしてメシア到来への切実な希望が入り混じる地でした。
この記事ではキリストがいた時代を探り、救い主とその教えを受けた人々を取り巻いていた日常生活や困難、雰囲気をよりよく理解していきましょう。
外国の支配下にあった人々:政治と緊張
当時のイスラエルはローマの支配下にありました。それでもイスラエルの人々が宗教的な慣わしを守ることはかなり自由でしたが、本当の意味で自由ではありませんでした。
しかし同時に、これはパクス・ロマーナというローマの支配による平和、強国による押しつけの平和の時代でもありました。その状況がキリストの伝道と教会設立に有利な条件を生み出したのでした。宗教が異なる帝国の真ん中で、生ける神を信じていたのはイスラエルの民だけだったのです。
ユダヤ社会にはいろんな派閥が存在していました。ハロルド・ウィルミントンがリバティ大学で発表した『イエス・キリストの時代の政治的・宗教的集団』という記事から次のことを学ぶことができます。
- サドカイ人は貴族階級で、神殿祭司が多く、ローマと協力していました。彼らは記録されていた律法のみを受け入れ復活を否定したため、イエスと真っ向から対立しました。
- パリサイ人は多数派で、モーセの律法と伝承を厳格に守りましたが、イエスが罪人と交わり、安息日に癒しを行ったことから最も激しい批判者となりました。
- 熱心党(ゼロテ派)は武力でローマへの反乱を訴える愛国者であり、ヘロデ党はヘロデ王家とローマとの協力こそが生き残りの道だと考え、王朝を支持していました。
聖典が明かすもの
イエスはそのような緊張の時代の中で伝道し、どの政治勢力にも加わりませんでした。この世のものではない神様の国について語ったとき、イエスは民を圧迫する政治的解決ではなく霊的な解決を提示したのです。
最初の1世紀のユダヤは暴力に満ちていました。ローマの平和は軍事力によって維持され、ヨセフスのような歴史家たちの記録には、反乱や十字架刑の脅威が数多く記されています。聖典にもその緊張が垣間見えます。例えば、ピラトがガリラヤ人の血を彼らのいけにえに混ぜた出来事は残酷な抑圧の証です。
また善きサマリヤ人のたとえ話は、旅人が危険な道で襲われ死にかけたという当時の治安の悪さを映し出しています。
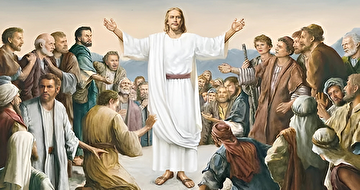
ガリラヤの日常生活:仕事・家族・社会
多くの人々は貧しく、厳しい労働をしていました。農業が生活の中心であり、それが種まきのたとえなどに反映されています。羊飼いもイスラエルにとって謙遜で重要な身分だったため、イエスはご自身をよく羊飼いにたとえていました。
ガリラヤでは漁業も重要で、ペテロやアンデレのような使徒たちが働いていました。大工(イエスと父ヨセフの職業)などの職人も一般的で、「テクトン」というギリシャ語は、石工も意味するかもしれません。
イエスが漁師、取税人、熱心党員といった多様な人々を弟子に召したのは、福音がすべての人のためであることを示していました。家族が社会の基盤だったため、家族なしの生活はほとんど不可能でした。
社会的な地位や機会から追放されることは孤立を意味しました。特にサマリヤ人は、数百年の歴史的・神学的対立からユダヤ人と深い敵意を持っていました。そのため、イエスが彼らに手を差し伸べたことは革命的であり、「誰もが神様に愛されている」ことを示す大胆な行為でした。
経済的には生活は不安定でした。1日の賃金はわずか1デナリだったそうです。今の価値でいうと1万円程度という説もありますが、税金は収入と比べると重く、借金は当たり前になっていたため、家族を養うのは大変厳しかったそうです。赦さない僕のたとえ話は、その背景を映し出しています。
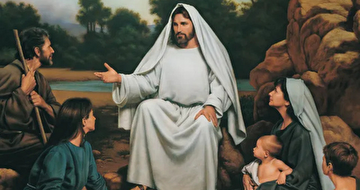
素朴な習慣と意味ある伝統
村は小さく、石や粘土で造られた家に住み、平らな屋根は作業や休息に使われました。食事は大地が与えるもの、パン、オリーブ、オリーブ油、果物、魚が中心でした。
当時、一緒に食事をすることは「親しい仲間として受け入れる」という大切な意味がありました。ですから、イエスが人々から嫌われていた取税人や罪人と食卓を囲んだのは、その人たちをも神様は愛していると示す、とても大胆で衝撃的な行動だったのです。
人々の衣服はとても実用的で、普段は羊毛や亜麻で作ったチュニックに外套を羽織るのが一般的でした。長血の女が癒された物語は、イエスの衣のすそに触れるだけでも大きな力があったことを思い出させます。
安息日が終わると、人々は喜びを分かち合い、過越の祭のような宗教的なお祭りのときには、家族でエルサレムへ巡礼しました。信仰と楽しみはいつも結びついていたのです。
また、この地域では多くの言語が使われていました。通りではアラム語が話され、会堂ではヘブライ語が唱えられ、商売にはギリシャ語が使われ、ローマの役人はラテン語を使っていました。
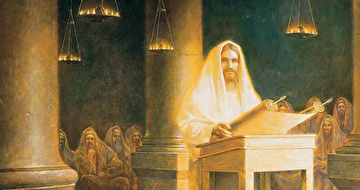
信仰によってイエスの時代に生きる
何よりも宗教が生活を導いていました。神殿は犠牲の場であり、会堂は祈りと教えのための集会所のような存在でした。
レビ人は神殿の務めを行い、律法学者は聖典を学び解釈し、大抵パリサイ人と共にキリストに反対しました。
宗教的な最高議会であるサンヘドリンは、イエスを裁くときに自分たちの律法を破り、不公平な裁きを行いました。しかし、形式ばかりの伝統や分裂に疲れた人々を、イエスは優しく招きました。
すべて重荷を負うて苦労している者は、わたしのもとにきなさい。あなたがたを休ませてあげよう。
マタイによる福音書11章28節
イエスの時代の世界は複雑で厳しく、傷ついていました。その中でイエスがもたらした光はいっそう明るく輝いたのです。イエスが来たのは完璧な世界ではなく、現代のように問題を抱えた現実の世界でした。だからこそ、イエスがガリラヤで伝えられた希望は今も必要とされ、時を超えてもシンプルで分かりやすく、癒しを与え続けているのです。


